アドリブをするのに必要なこの「思ったことを音にする」というのはどういう風にすればいいのかとかなと昨日から考えていました。
“思ったことを音にする訓練” の続きを読む
カテゴリー: 鍵盤ハーモニカ
季刊ケンハモと、新しい鍵盤ハーモニカ本

「季刊ケンハモ」という鍵盤ハーモニカの自費出版本を、過去5冊刊行していたことがあります。今(2018年)から13年程前の2005年頃の話です。
この時は「今の状況のアーカイブ化」という目的で作っていました。フリーターで朝から夜まで立ち仕事をした後家に帰って徹夜で写植するという今では考えられないことを連日やっていました。今なら原稿も入稿もデジタルで出来るので楽になったなと思います。
刊行当時と今では鍵盤ハーモニカを取り巻く状況がまるで違い、書かれた内容は全て過去のものとなってしまっています。当時の自分の見積もりでは今みたいな状況になるまであと10年は要ると考えていました。当初のアーカイブ化という目的は「過去の産物」という別の意味で果たされてしまっていると感じています。
で、最近また鍵盤ハーモニカの自費出版本を作れないかなと考えるようになりました。ただ内容が問題で、今の多様化したシーンに対してより幅広く対応できるトピックは何だろうとと悩んでいます。大体こういうの「自分の好きなものをやるといい」とか言われたりするのですが……作品ではないのできちんとニーズを考えたいですね。
現在の所、
・アーティストにスポットを当てる
・楽器の構造の話
・メンテナンス方法
・いずれかのモデルにスポットを当てた特集
等々、色々考えてはいます。季刊ケンハモではアーティストの方に寄稿頂いたのですが、次やるとしたら自分で本文を作っていくことになると思います。いつ出せるか分かりませんが、確定次第何らかのアナウンスが出来ればと思っています。
鍵盤ハーモニカ唄口カスタム
ジャズのワークショップに行ってきました

昨日ジャズのワークショップにケンハモで参加してきました。
ジャズは聴きはするのですが実際に演奏に参加するのは初めて、というかもう完全に門外漢で、今までやってきた音楽とは全然違う文化で文字通り右も左も分からない状態でした。ケンハモでジャズって2000年頃から聞きますけど、実際やってる人って少ないですよね。
ジャズに合いそうかなということで持って行ったのはW-37だったのですが、周りの方の反応が好意的でよかったです。ワークショップの講師の先生も以前からケーブル繋げるヤツを触ってる(PRO-44系だと思います)そうで、それだけで嬉しかったり。
以前から気になっていたアドリブについての基礎を教わりました。その他実演奏でアドリブやったり。ただ曲が全然分からないのでそういう所も勉強しないとなーと感じています。曲集買おう……。
あとアドリブの講評で和音取り込んだらいいんじゃないかと言われたのですが、実は和音がとても苦手で大きな課題が出来ました。コードの形がパッと出てこないんですけど、ジャズピアニストの方とかコードってどうやって覚えるんでしょう?そういった所も課題です。
来月もう1回あるとのことで、ワークショップで言われた内容のメモとにらめっこしながら再挑戦です。
HAMMOND PRO-44H
HAMMOND PRO-44H
 昨日に引き続きケンハモの話。
昨日に引き続きケンハモの話。
今日はご存知PRO-44Hについて。W-37と違い、こちらはかなり手を加えています。
■44鍵の鍵盤ハーモニカ
PRO-44Hは、モデル名通り44鍵の鍵盤ハーモニカで、その音域は国際式でC3~G6とかなり広くなっています。37鍵に比べて下はC3~E3の5音、上はF#6、G6の2音が増えています。音域が広いため両手弾きにも優れています。
以前は「ハモンド44」という名前が付いていたのですが、現在はPRO-44Hで統一しているみたいです。また、姉妹モデルとしてPRO-44HPというモデルもあります。
■エレアコ鍵盤ハーモニカ

もう1つの特徴として、ケーブルでアンプ等に繋げて音を出せるという機能があります。エレキギターと同じ機材(エフェクターとか)を使うことが出来るので、ハウリングを起こさなければエフェクト音も自由自在です。
その他エレアコでPCへケーブルで音を入力することも可能で、これを利用して録音して曲を作ることもあります。便利です。
■キーの沈み込みが浅い
「滑らかなキータッチ」のような表現をすることが多いのですが、キーの沈み込みが他のモデルに比べて浅くなっています。(深い)M-37C他>PRO-37V2>PRO-44H(浅い)という感じです。
これによりスムーズな運指が可能になります。反面空気の通り道であるバルブの開きが小さくなることから特に強く吹いた時に音量が上がらないといったデメリットもあります。
逆に言えばたくさんのキーを押す両手弾きや和音を多用する場合は息が持ちやすいということにもなり、そういった演奏をする場合はメリットになるでしょう。
というPRO-44Hですが、自分は基本的に両手弾きでの演奏を前提にセッティングしています。以前はこの1台で全て賄おうとしたのですが、W-37を導入したことで役割分担が出来たという感じです。両手弾き用としていくつかカスタムしてします。
■カスタムいろいろ
 まずストラップピンの位置。通常はサイドカバーの両端ですが、カバー固定ネジがM3ネジであることを利用して長いネジを入れてロックストラップピン(ワンタッチで取り外しができるもの)を付けています。
まずストラップピンの位置。通常はサイドカバーの両端ですが、カバー固定ネジがM3ネジであることを利用して長いネジを入れてロックストラップピン(ワンタッチで取り外しができるもの)を付けています。
いろんなピン位置を試してみたのですが、穴を開けなくていいことや楽器を下から支えることで安定性が高いのが気に入ってこの方式を採用しています。ロックストラップピンも便利なので勧めたいんですけどなかなか良さを分かってもらえません。

それから唄口も加工しています。下を見やすいようにL字ジョイントと卓奏唄口の咥える部分を貼り付けています。また、タンギングなどでホースが暴れるのを抑えるためホースに布を巻いています。
あとはカラーですが、塗装ではなくカッティングシートを使っています。こういったカスタムは得意分野なので,ケンハモサイトを開設したら真っ先に充実させたいですね。
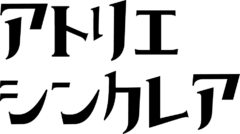
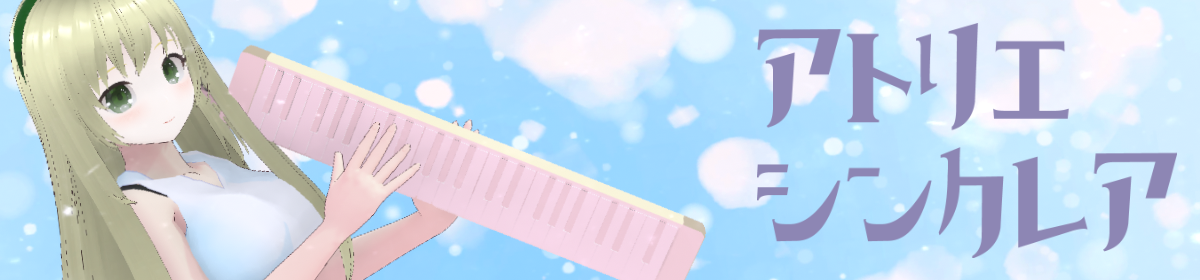

 先日使い始めたS型唄口MP-151。
先日使い始めたS型唄口MP-151。

